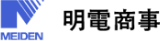電子帳簿保存法の歴史

2022年1月に電子帳簿保存法の改正が行われることで、対応を検討されている企業からの相談を頂いていますが、 法改正の歴史と法改正を行う理由を紹介させて頂きます。
1.電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法とは、
国税関係帳簿書類の保存を、紙文書でなく電子データとして保存することを認めた法律になります。
紙ではなく電子データによる書類の保存を容認することで原本の紙の書類を破棄でき、
帳簿管理の負担の軽減やペーパーレスの推進を目的に制定されました。
正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」となり、
この法律が制定されるまでは会計帳簿や決算書などの書類は紙で保存していました。
また、電子データがあっても紙に印刷して保存していた企業も多かったですが、
こういった紙の書類や手続きの電子化を促進するのが、電子帳簿保存法になります。
2.電子帳簿保存法の法改正が都度行われる理由
電子帳簿保存法が施行されたのはWindows98が発売された1998年となりますが、
その頃はまだインターネットも日本全国の企業に普及しているとは言えない状況でしたし、
回線もまだまだ遅いのが当たり前でストレスの溜まるものでした。
また、デバイスにおいても今のものとは比較にならないほど低いスペックでした。
ソフトウェアも今と比較すれば正に黎明期と言えるものでした。
そんな中で施行された法律がそのまま活用される方が、逆に考えるとあり得ないことであり、
回線スピードやデバイスの進化やITの進化による解釈の変化によって都度、法改正が行われています。
10年後は私たちが思いもしない様な取り組みが、当たり前になっている可能性もあるかもしれません。
3.2022年1月の法改正の主な目的
電子帳簿保存法というと、なんとなく尻込みをされていた企業があったり「ウチは違う」といった声も伺ったりしましたが、
政府が推進する「ペーパーレス化」に電子帳簿保存法は切っても切れない関係ですし、
コロナウイルスによる緊急事態宣言以降の「テレワーク化」の推進も進んでいます。
文書を紙で保存(保管)するよりも電子データで保存(保管)する方が楽です。
保管のためのスペースも取りません。
保管場所だけでなく、文書を探す手間も大幅に楽になることでコスト(場所・人件費)も削減できますし、
セキュリティが担保されていれば、会社に行かずとも
インターネット回線が繋がっていればテレワーク(在宅)や出張先でも対応が可能となります。
しかし、そんなメリットが多々あるはずの電子化が、まだまだ導入に至っていない企業が多い背景として、
導入するうえでの足枷(制約)が多かったことが挙げられます。
その中で最も大きな障害になっていたのが、
「税務署による事前承認」が必要であるということです。
従来までの法制度では、電子データでの保存を行なうにあたって
運用開始の3ヶ月前までに所轄の税務署で手続きを行う必要がありました。
さらに電子化に利用するシステム等を「承認申請書」に記載し、
処理の責任者や作業工程までを明記した「事務手続きの概要」の作成・提出が必要となっていました。
申請からの流れは申請書の提出からの3ヶ月間はその内容を精査される期間であり、
承認が得られるまで待機しなければならず施行できません。(却下されることもありました)
そういった手間と多くの負担がかかることから、導入を検討しても踏み切れない企業も多くありました。
因みにどれだけの企業が電子帳簿保存法についての申請を行っているのかを紹介しますと、
電子保存開始前の手続きに関しては、2020年3月時点で電子帳簿保存は約27万件、
スキャナ保存に関しては一気に数が減り約4,000件しか承認を受けていない状況でした。
日本に約360万の企業が存在する中で、承認を受けている企業が非常に少ないことが見て取れます。
折角、ビジネスにも環境にもメリットがあるのに利用企業が極端に少ないという現状を打破するためにも、
電子帳簿保存制度を抜本的に見直すことが求められ、
2022年1月施行の法改正では多くの企業が導入に踏み込めるように、大幅に要件が緩和されることとなります。

4.過去の法改正について
電子帳簿保存法が1998年に施行されてからの主な改正を時系列で紹介させて頂きます。
2005年改正:e-文書法の施行
紙での発行及び受領された国税関係書類(決算関係書類を除く)」を
スキャナで読み込み、電子データ化して保存することが認められました。
ただし、領収書や請求書は3万円未満の少額なものに限定されていました。
また、電子署名が必要となっており要件はまだまだ厳しいものでした。
2015年改正:金額の上限撤廃・電子署名不要・定期検査等の適正事務処理要件の追加
3万円未満となっていた金額の上限が撤廃となり、金額にかかわらず電子データ化することが可能となりました。
また、電子署名が不要になり、対象書類やスキャンに関する要件が大幅に緩和されました。
追加要件として適正事務処理要件が求められる様になり、
① 相互けんせい
② 定期的なチェック
③ 再発防止策
などの内部統制を適切に実施することが求められる様になりました。
2016年改正:スマートフォンで撮影した画像の認可
受領者の電子手続きの整備として、社外でスマートフォンによる領収書等の読み取りが可能となりました。
また、小規模企業者の相互けんせい要件の特例が施行され、
小規模企業者への定期チェックを税理士が行う場合は相互けんせい要件は不要となりました。
2019年改正:承認前の重要書類も税務署への届出により対象に
承認を受ける前に作成または受領した重要書類(過去分重要書類)が、
一定の要件を満たすことで対象となりました。
2020年改正:ユーザーが改変できないものはデータ保存が可能に
コーポレートカード等キャッシュレス決済の場合は領収書不要になり、
デジタルデータの利用明細が領収書の代わりとして認められるようになりました。
5.電子帳簿保存法に対応したサービス
freeeサイン
電子契約サービスですが、クラウド上に容量無制限の電子書類が保管できます。電子契約の推進と併せて進めることが可能です。
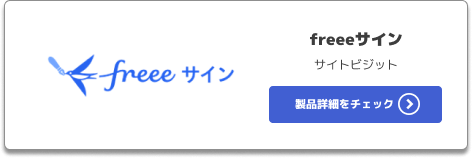
楽々DocumentPlus
電子データを保管し、日本語にマッチした検索機能によって電子データの管理を容易にします。また、ワークフローも搭載していますので複合的に業務改善を行うことが可能です。

6.まとめ
より便利な世の中(ビジネス環境)に繋がると思われます。
先ずは2022年1月電子帳簿保存法改正に対応することよって、
「ペーパーレス化」や「業務改善」を劇的に進めていくことが可能となります。
明電商事では今回の改正に対応しているサービスを取り扱っておりますので、
取り組みを進める際は是非ともお声掛け下さい!